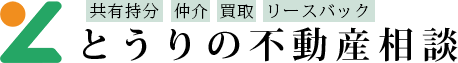相続人とは?不動産相続の注意点を解説
故人の財産や負債を引き継ぐ権利を持つ人々のことを指します。
相続には多くの法律や手続きが関わっており、その範囲や相続権について理解することは非常に重要です。特に不動産相続は、しばしばトラブルの原因となることがあります。本記事では、相続人の範囲や相続権について詳しく解説し、兄弟姉妹も相続人となるのか、不動産相続の注意点、不動産を相続した際のトラブルについて掘り下げていきます。

相続人の範囲と相続権
相続人の範囲は、民法により厳密に定められています。一般的に、相続人は以下のように分類されます。
1. 配偶者
配偶者は常に相続人となります。これは、故人と法律上の婚姻関係にある人物を指します。なお、事実婚のパートナーは法律上の配偶者と認められないため、相続権はありません。事実婚のパートナーに財産を渡したい場合は、事前に公正証書遺言などをしておくことで対処できます。
2. 子供
子供は第一順位の相続人です。故人の実子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。子供が複数いる場合、均等に相続分が分けられます。
3. 直系尊属
故人の両親や祖父母などの直系尊属は、子供がいない場合に相続人となります。親が健在であれば親が相続しますが、親が故人の場合は祖父母が相続権を持ちます。
4. 兄弟姉妹
子供や直系尊属がいない場合、故人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となります。
兄弟姉妹も相続人になるのか?
先述の通り、子供や直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。生涯結婚しない人が増え、人生100年時代と言われる今、自分の兄弟姉妹が相続人となるケースはこれから増えるでしょう。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供である甥や姪が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と呼びます。
不動産相続の注意点
不動産相続には特有の注意点があります。まず、不動産は、お金と違い分割が難しいため、相続人間でのトラブルの原因となりやすいです。また、遺産総額によっては相続開始の日の翌日から10か月後に支払わなければならない相続税や不動産登記手続きなどが必要となるため、事前に十分な準備と計画が求められます。
1. 相続税
不動産を相続する際には相続税が課されます。不動産の評価額に基づいて相続税が算出されるため、高額な相続税が発生することがあります。相続税の計算は複雑で、控除や特例を適用することで減額できる場合もあります。以下に具体的な相続税の計算例を示します。
例:故人が所有していた不動産の評価額が1億円、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合
- 基礎控除額:3000万円 + 600万円 × 相続人の数(3) = 4800万円
- 課税対象額:1億円 – 4800万円 = 5200万円
この課税対象額に対して、相続税の税率(10%から55%までの累進課税)が適用されます。具体的な税率は課税対象額により異なりますので、詳細は税理士や専門家に相談してください。
2. 登記手続き
不動産を相続した場合、所有権の変更登記が必要です。登記を行わないと、第三者は真の所有者が誰だかわかりません。また相続人間でのトラブルや売却時に問題が生じる可能性があります。登記手続きは司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
登記手続きの主なステップは以下の通りです。
- 相続人の確定:戸籍謄本や遺言書を用いて相続人を確定します。
- 不動産の評価:固定資産税評価額を基に不動産の評価を行います。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
- 登記申請:法務局にて所有権移転登記の申請を行います。
3. 分割方法
不動産の分割は困難なため、相続人間での協議が必要です。一つの不動産を複数の相続人で共有する場合、それぞれの持分を明確にすることが重要です。不動産を売却して現金で分割する方法もありますが、その際には売却の手続きや費用がかかります。以下に、いくつかの分割方法を紹介します。
- 共有名義:相続人全員で不動産を共有する方法。それぞれの持分を明確にし、共有持分に基づいて運用や売却を行います。
- 分割登記:不動産を物理的に分割し、相続人ごとに所有権を登記する方法。土地の形状や建物の構造により実現が難しい場合があります。
- 売却分割:不動産を売却し、得た現金を相続人間で分割する方法。売却手続きや費用が発生しますが、現金化することで分割が容易になります。
不動産を相続した時のトラブル
不動産相続には、多くのトラブルが伴うことがあります。以下に、代表的なトラブル事例とその対策を紹介します。
1. 相続人間の意見対立
不動産の相続では、相続人間での意見対立が頻発します。特に共有名義での相続や売却時の意見が一致しない場合、トラブルが発生しやすいです。いざトラブルが発生した場合は、合意するまで長期間要する場合もあります。
2. 登記手続きの遅延
相続登記を怠ると、第三者は不動産の所有者が誰だかわかりませんので、売却や担保設定が困難になります。また、将来的に登記手続きを行う際には、相続人が増えたり、所在不明の相続人が出てくるなど、手続きが煩雑化することがあります。共有でもいいので速やかに登記手続きを行うことが重要です。
3. 相続税の支払い
不動産相続には相続税がかかりますが、高額な相続税を支払うことが困難な場合があります。高額の相続税を支払うために金融機関から借り入れを起こしたり、借りられない場合は一時的にノンバンクに借りるなどして、相続税を用立てる方が多いようです。事前に相続税の資金計画を立てておくことが重要です。
4. 不動産の管理
不動産を相続した後、その管理も重要な課題となります。相続人全員で不動産の管理方針を決定できたら一番いいですが、私が担当した相続不動産案件は相続人全員で管理方針を決定した話は一度も聞いたことがないです。なぜなら弊社に来る案件は円満相続というよりは、トラブルを抱えた相続案件しかこないからです。
5. 不動産の評価
不動産の評価額は、相続税の計算や登記手続きに大きく影響します。適切な評価額を把握するためには、固定資産税評価額や路線価を参考にすることが一般的です。相続税計算は税理士の専門分野ですが、不動産評価額は専門の不動産鑑定士に依頼することがおすすめです。
まとめ
相続人の範囲や相続権、不動産相続の注意点、そして不動産を相続した際のトラブルについて詳しく解説しました。不動産相続は複雑で、多くの問題が伴うことが多いですが、事前の準備と計画が重要です。相続不動産に関する疑問や不安がある場合は、とうりの不動産相談へご相談ください。
とうりの不動産相談 宅建士 石川